万年筆とつけペン、どちらもインクを使って文字を書く筆記具ですが、その違いを正確に説明できるでしょうか。「万年筆をつけペンとして使うことはできるの?」あるいは「それぞれの特徴や違いがよくわからない」と感じている方も多いかもしれません。独特の書き味を持つこれらの筆記具は、デジタルでのコミュニケーションが主流の現代だからこそ、自分の手で文字を綴る「書く楽しさ」を再発見させてくれる、奥深い魅力を持ったアイテムです。
この記事では、万年筆とつけペンの構造的な違いといった基本的な知識から、それぞれのメリット・デメリット、さらには万年筆をつけペンとして代用する場合の具体的な方法と注意点まで、一歩踏み込んで詳しく解説します。また、近年人気を集めている「万年筆のペン先を持つつけペン」という新しい選択肢についても、具体的な製品を比較しながらご紹介しますので、あなたの筆記具選びの確かな指針となるはずです。
- 万年筆とつけペンの構造やインク補充方法の根本的な違い
- それぞれのメリット・デメリットと最適な利用シーン
- 万年筆をつけペンとして使う際の具体的な方法と注意点
- 最新の人気モデル「いろうつし」と「hocoro」の徹底比較
万年筆とつけペンの基本的な違いを解説
この章で解説する内容
- 構造で見る万年筆とつけペンの違い
- インク補充方法とメンテナンスの違い
- つけペンのメリットとデメリット
- 万年筆のメリットとデメリット
- 万年筆をつけペンとして使うのは可能か
- 万年筆をつけペン代わりにする注意点
構造で見る万年筆とつけペンの違い
万年筆とつけペンの最も大きな違いは、インクを本体内部に貯蔵し、自動で供給する機能があるかどうかです。この構造の違いが、書き味、実用性、そしてメンテナンス方法のすべてに大きく影響しています。
万年筆の心臓部とも言えるのが「ペン芯」です。ペン芯にはインクを保持し、空気と交換しながらペン先へと送るための非常に細かい溝が刻まれています。この溝が毛細管現象を利用して、インクを絶え間なくペン先へ供給するのです。これにより、一度インクを補充すれば、長時間の安定した筆記が可能になります。ペン先にはペンポイントと呼ばれる硬い金属(主にイリジウム合金)の玉が溶接されており、これが紙の上を滑ることで、万年筆特有の滑らかな書き心地が生まれます。
一方、つけペンにはこのペン芯が存在しません。そのため、ペン先を直接インクボトルに浸して、ペン先の表面やスリット(切れ込み)にインクを付着させて筆記します。インクを保持する力は弱いため、一度に書ける文字数は限られ、こまめにインクを付け直す必要があります。ペン先とペン軸が分かれているものが多く、Gペンや丸ペンなど、漫画やイラスト、カリグラフィーといった用途に応じてペン先を自由に交換できるのが大きな特徴です。
つまり、万年筆は「インクタンクを内蔵した自己完結型の筆記具」で連続筆記に強く、つけペンは「インクを外部から都度供給するシンプルな筆記具」でインク交換の手軽さに優れる、と理解すると分かりやすいですよ。
インク補充方法とメンテナンスの違い
インクの補充方法とメンテナンスの手間も、両者を選ぶ上で重要なポイントです。万年筆は、インクが充填された樹脂製の筒を交換する「カートリッジ式」、ペン先から直接ボトルインクを吸入する「吸入式」、そしてカートリッジとインク吸入器(コンバーター)を付け替えられる「両用式(コンバーター式)」があります。いずれも一度補充すれば、インクがなくなるまで書き続けられる実用性の高さが魅力です。
ただし、インクの色を変えたい場合は、内部のインクをすべて抜き、ペン先やペン芯を念入りに洗浄・乾燥させる必要があります。コンバーターを使って水を繰り返し出し入れしたり、一晩水に浸け置きしたりと、作業にはそれなりの時間がかかります。
対して、つけペンはペン先をコップの水などで洗い、ティッシュや柔らかい布で拭くだけで、数秒でインクの色を変えられます。ペン芯のような複雑な部品がないため、洗浄は非常に手軽です。様々な色のインクを少しずつ、気分に合わせて楽しみたい「インク沼」の住人にとっては、この圧倒的な手軽さが最大の魅力と言えるでしょう。
つけペンのメリットとデメリット

ここでは、つけペンの持つ魅力と、使用する上での注意点をより詳しく解説します。この特性を理解することが、つけペンを最大限に楽しむコツです。
つけペンのメリット
- 手軽さ:インクボトルさえあれば、思い立った時にすぐ書き始められます。複雑な準備は必要ありません。
- インク交換の圧倒的な容易さ:ペン先を水で洗うだけで、すぐに別の色のインクを試せます。ラメ入りなど、万年筆では扱いにくいインクも気軽に楽しめます。
- 表現の豊かさ:インクの付け方や筆圧で、線の太さや濃淡、インクのかすれなどを意図的に表現できます。特にGペンのような弾力のあるペン先は、筆圧による線の強弱がつけやすく、イラストや漫画制作でプロにも愛用されています。
- コストパフォーマンス:ペン軸もペン先も比較的安価なものが多く、数百円から始められるため、初期投資を抑えてインクの世界に足を踏み入れることができます。
つけペンのデメリット
- インク持ちが悪い:構造上、こまめにインクを付け直す必要があり、長文の筆記には集中力が途切れがちです。
- ボタ落ちのリスク:インクを付けすぎたり、ペン先を紙に置いたままにしたりすると、インクの塊が「ボタッ」と落ち、作品を汚してしまうことがあります。ペン先をインク瓶の縁で軽くしごく、といったコツが必要です。
- 携帯性の低さ:インクボトルとセットで持ち運ぶ必要があり、蓋の緩みなどによるインク漏れのリスクもあるため、外出先での気軽な使用には不向きです。
万年筆のメリットとデメリット

次に、万年筆のメリットとデメリットを掘り下げて見ていきましょう。実用性と、手間すらかける喜びをくれる奥深さが同居しています。
万年筆のメリット
- 長時間の快適な筆記:一度のインク補充で長く書き続けられ、軽い筆圧で書けるため、長時間の筆記でも手が疲れにくいです。思考を止めずにアイデアを書き出すシーンなどで真価を発揮します。
- 優れた携帯性:キャップをすればインク漏れの心配も少なく、手帳や胸ポケットに挿してスマートに持ち運べます。ビジネスシーンでも活躍します。
- 唯一無二の滑らかな書き心地:ペンポイントが紙の上を滑る独特の感覚は、万年筆ならではの魅力です。使うほどに自分の書き癖に合わせてペン先が馴染み、「ペンを育てる」感覚を味わえます。
- 所有する喜び:美しいデザインや精巧な機構を持つモデルが多く、単なる筆記具を超えた工芸品としての魅力があります。大切な人への贈り物としても最適です。
万年筆のデメリット
- メンテナンスの手間:インク詰まりを防ぐため、定期的な洗浄が必要です。特に顔料インクなどを使った場合は、こまめな手入れが欠かせません。
- インク交換の手間:前述の通り、インクの色を変える際には、洗浄と乾燥に時間がかかります。
- 初期コスト:数千円から数十万円と価格帯が広く、つけペンに比べると一般的に高価な製品が多いです。
- 乾燥に弱い:しばらく使わないでいると、ペン先付近のインクが乾いて書けなくなることがあります。
万年筆をつけペンとして使うのは可能か

結論から言うと、万年筆をつけペンのように使うことは可能です。具体的には、インクカートリッジやコンバーターを装着しない空の状態で、ペン先だけをインクボトルに浸して筆記します。これは、新しいインクの色味を少しだけ試したい時などにも便利な方法です。
この使い方をすると、本来インクを供給するためのペン芯が、一時的にインクを保持する「リザーバー」のような役割を果たします。そのため、ペン芯のない通常のつけペンよりもインク持ちが格段に良くなり、インクのボタ落ちも起こりにくくなります。
インク詰まりなどで使わなくなった万年筆を、特定の色のインク専用の「ちょっとリッチなつけペン」として第二の人生を歩ませるのも、素敵な活用法の一つです。
万年筆をつけペン代わりにする注意点
万年筆をつけペンとして使う際には、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。最大の問題は、一度ペン芯に入り込んだインクは、完全には洗浄しきれない可能性があるという点です。
ペン先をインクに浸すと、毛細管現象によってペン芯の複雑で微細な溝の奥深くまでインクが入り込みます。このインクは、水で軽くすすぐ程度では到底落ち切りません。特に、色の濃いインクや染料の粒子が大きいインクは、ペン芯に色が沈着してしまうこともあります。
洗浄が不十分なまま別の色のインクを付けると、色が混ざってしまい、せっかくの美しいインクの色を楽しめなくなります。特に淡い色のインクを使おうとすると、前に使ったインクの色が滲み出てきてしまうでしょう。
つけペン代わりにする際の最大の注意点
頻繁にインクの色を変えたい、というつけペンの醍醐味を味わいたい用途には全く向いていません。もしこの使い方をするのであれば、「この万年筆はこのインク専用のつけペンにする」と固く決意し、割り切って使うことを強くおすすめします。そうすれば、インク持ちが良くボタ落ちしにくい、高性能なつけペンとして快適に活用できます。特に、耐水性・耐光性に優れるものの詰まりやすい「顔料インク」を試す際には、この使い方に限定すべきです。
万年筆とつけペンのハイブリッド!最新モデルを紹介
この章で解説する内容
- 万年筆メーカー製つけペンが人気の理由
- パイロット「いろうつし」の特徴
- セーラー「hocoro」の特徴
- 「いろうつし」と「hocoro」を比較
- あなたに合う万年筆・つけペンの選び方
万年筆メーカー製つけペンが人気の理由

近年、つけペンの手軽さと万年筆の滑らかな書き心地を両立させた「万年筆ペン先のつけペン」が、文房具市場で大きな注目を集めています。これは、パイロットやセーラー万年筆といった国内の大手万年筆メーカーが、長年培ってきた技術を注ぎ込んで開発した、新しいカテゴリーの筆記具です。
人気の理由は、ペン芯がないため洗浄が驚くほど簡単で、気軽にインクの色を交換できるつけペンの良さを持ちながら、ペン先には摩耗に強い「ペンポイント」が付いた万年筆用のステンレスペン先を採用している点にあります。これにより、従来の安価なつけペンのように「使っていくうちにペン先が削れて書き味が変化してしまう」という心配が少なく、万年筆特有の安定した滑らかな書き心地を、手頃な価格で長く楽しめるのです。
多彩なボトルインクをコレクションする「インク沼」の流行と共に、インクコレクターや文房具好きの間で「インクを気軽に楽しむための最適解」として、瞬く間に人気アイテムとなりました。セーラー万年筆の「hocoro」は、その優れたデザイン性と機能性から2022年度の「グッドデザイン賞」を受賞するなど、専門家からも高い評価を得ています。
パイロット「iro-utsushi<いろうつし>」の特徴
パイロットから発売されている「iro-utsushi<いろうつし>」は、誰にでも扱いやすいシンプルさと、万年筆の書き味を手軽に体験できるカジュアルさが最大の魅力です。ペン先は、同社のロングセラー入門万年筆「kakuno(カクノ)」に近い形状で、硬質で安定した書き味を提供してくれます。
主な特徴
- 王道のスタンダードなペン先:字幅は手帳やノートへの筆記に最適な細字(F)と、インクの濃淡をより楽しめる中字(M)の2種類。初めて万年筆ペン先を使う人にも違和感なく扱えます。
- 選べる2種類のペン軸:非常に手頃な価格の樹脂軸(クリアブラック、クリアブルー、ノンカラー)と、天然のハードメイプル材を使用し、温かみのある握り心地の木軸(モクメ、ブラック)から選べます。
- 親しみやすいデザイン:樹脂軸は下部がぷっくりと膨らんだ可愛らしいフォルム。ペン先を保護するキャップも付属しており、ペンケースに入れて安全に持ち運べます。
「万年筆に興味があるけれど、メンテナンスが大変そうで一歩踏み出せない」と感じている方の入門用として、まさにおすすめの逸品です。まずはいろうつしで、万年筆ペン先の滑らかな世界を気軽に体験してみてはいかがでしょうか。
セーラー万年筆「hocoro(ホコロ)」の特徴
セーラー万年筆の「hocoro(ホコロ)」は、ペン先を自由に付け替えられるユニークな機構と、ユーザーの使いやすさを追求した設計が特徴で、より創造的でマニアックな楽しみ方ができる製品です。
主な特徴
- 表現の幅を広げる多彩なペン先:通常の細字に加え、縦が太く横が細い線を描けるカリグラフィー用の「1.0mm幅」「2.0mm幅」や、筆圧や角度で自在に線の強弱を付けられる「筆文字」など、個性的なペン先が別売りで用意されています。
- 筆記距離を伸ばすリザーバーパーツ:インクの消費が激しい太字幅のペン先用に、インクの保持力を高める「リザーバー」という部品が用意されており、後付けすることでより長く、安定した筆記が可能になります。
- 細部まで考え抜かれたデザイン:ペン軸は自然な筆記角度に導くくびれのある形状。使わない時はペン先を逆向きに差し込んで本体に収納でき、安全かつコンパクトに持ち運べるなど、使う人のことを考えた工夫が随所に見られます。
特に「筆文字」ペン先などは、スチールペンとは思えない独特の”しなり”を感じる書き味で、文字やイラストに豊かな表情をつけたい方にぴったりです。一つの軸で様々な表現に挑戦したい、こだわり派のあなたにおすすめです。
「いろうつし」と「hocoro」を比較

どちらの製品も非常に魅力的ですが、コンセプトが異なるため、どちらが自分に合っているか迷う方もいるでしょう。ここでは、両者の特徴を項目別に整理し、比較検討しやすくまとめました。
| 項目 | パイロット「いろうつし」 | セーラー万年筆「hocoro」 |
|---|---|---|
| コンセプト | 万年筆の書き味を手軽に試せるカジュアルさとシンプルさ | ペン先交換で多様な表現を追求できるカスタマイズ性と専門性 |
| ペン先の種類 | 細字(F)、中字(M)の2種類 | 細字、1.0mm幅、2.0mm幅、筆文字など(交換式で拡張性が高い) |
| ペン軸の素材 | 樹脂、木 | 樹脂 |
| 価格帯(参考) | 樹脂軸:539円~、木軸:1,386円~ | ペン軸・ペン先セット:1,430円~(ペン先単体は717円~) |
| おすすめのユーザー | 万年筆初心者、手軽にインクを楽しみたい人、デザイン性を重視する人、プレゼントを探している人 | 文房具好き、カリグラフィーやイラストを描く人、一つの道具を多機能に使いたい人 |
「まずは気軽に万年筆のような書き心地とインクの色を楽しんでみたい」という方には、シンプルで価格も手頃な「いろうつし」が最適です。一方、「文字やイラストで、より豊かな表現を追求したい」というクリエイティブな目的がある方には、ペン先交換で可能性が広がる「hocoro」が強力な相棒となるでしょう。
あなたに合う万年筆・つけペンの選び方
これまで解説してきた内容を踏まえ、あなたの目的やライフスタイルに最適な一本を選ぶための最終的なポイントをまとめました。筆記具選びは、あなたが「書く」という行為に何を求めるかを見つめ直す良い機会にもなります。
目的別おすすめリスト
- とにかくたくさんの色のインクを手軽に楽しみたい
→ 洗浄が簡単なつけペンや万年筆ペン先のつけペン(いろうつし、hocoro)が最適です。インク沼に深く浸かりたいなら、これ以上の選択肢はありません。 - 手帳やノートに、日常的に文字を書きたい
→ 携帯性に優れ、長時間の筆記でも疲れにくい万年筆がおすすめです。思考のパートナーとして、日々の生活に寄り添ってくれます。 - イラストやカリグラフィー、アートな文字で表現を楽しみたい
→ 様々なペン先で多彩な線を描ける伝統的なつけペンや、特殊ペン先が揃うhocoroが、あなたの創造性を最大限に引き出します。 - 万年筆の購入を検討しているが、まずはお試しで使ってみたい
→ 非常に手頃な価格で万年筆の本格的な書き心地を体験できるいろうつしから始めるのが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
最後に、この記事の要点をリスト形式で振り返ります。このポイントを押さえておけば、あなたも今日から万年筆とつけペンの違いを明確に語れるようになるはずです。
- 万年筆とつけペンの最大の違いはインクを内部に貯蔵するペン芯の有無
- 万年筆はペン芯の働きでインクを自動供給し長時間の筆記が可能
- つけペンはペン先を都度インクに浸す必要がありインク交換が容易
- 万年筆のインク補充にはカートリッジ式、吸入式、コンバーター式がある
- 万年筆の色交換はペン芯の洗浄に時間がかかる
- つけペンはペン先を水洗いするだけで手軽に色を変えられる
- 万年筆をつけペンとして代用することは可能だが推奨はされない
- 代用するとペン芯の洗浄が困難なため特定の色専用と割り切るべき
- 近年は万年筆のペン先を持つつけペンが人気を集めている
- 万年筆の滑らかな書き心地とつけペンの手軽さを両立した良いとこ取りの製品
- 代表的な製品にパイロットの「いろうつし」とセーラー万年筆の「hocoro」がある
- 「いろうつし」はシンプルでカジュアルなため万年筆初心者におすすめ
- 「hocoro」はペン先を交換できカスタマイズ性が高くクリエイティブな用途向き
- 日常的な筆記や携帯性なら万年筆、インクを気軽に楽しむならつけペンが最適
- 自分の目的やライフスタイルに合わせて最適な一本を選ぶことが最も重要
万年筆もつけペンも、それぞれに深い歴史と魅力があります。この記事が、あなたにとって最高のパートナーとなる一本を見つけるきっかけとなれば幸いです。ぜひ、お気に入りの筆記具とインクで、豊かなライティングライフをお楽しみください。






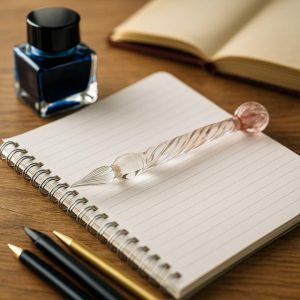


コメント